

| 猟奇に走る 小説を面白いと思って読み始めたのは、江戸川乱歩の本と出会ってからだ。 乱歩を読んだのは二十歳前の漫画青年の頃だった。そして乱歩の「猟奇の果て」をヒントにした漫画で月刊漫画ガロでデビューした。絵は水木しげるを真似、話は乱歩を真似た。 乱歩と出会ったとき、僕は大阪キタの東通り商店街という歓楽街の中にある本屋さんで働いていた。 乱歩を読んで、現実とは違うもう一つの世界を知ってしまった。そのためではないにせよ三ヶ月で会社を辞めた。 現実とは異なる世界とは、異次元の世界ではなく、フィクションの世界のことである。 乱歩の文章からほとばしり出る恐ろしいまでのロマンの香りを嗅いでしまった僕は、まさに猟奇に走ってしまったのである。 だが僕の場合、乱歩小説の登場人物のように、逸脱した趣味に走るほどのロマンチストにはなりきれなかった。 現実の上では猟奇に走るような雰囲気は何処を探しても見当たらないので、漫画の世界でそれをやろうと考えた。漫画を書く行為は現実の行為なのだが、書く行為そのものはフィクション的なのだ。現実の上に何かを書き込むのではなく、紙の上に書き込むのだから、この行為はあまり現実的だとは考えにくいのである。 当時学生運動も下火になっており、そういった社会を動かしてしまいそうなロマンを胡散臭く見ていた僕は、結局は現実逃避に走ったのである。つまり現実の上に書き込まれていくロマンよりも、書き込まれないロマンを求めていたのだろう。書き込まれることによってロマンは現実化され、ロマンがロマンではなくなってしまう。しかし最初から現実化出来ないロマン(妄想)がある。書き込んでも書き込んでも現実化出来ないロマンに僕は興味を抱いた。 当時の漫画雑誌ガロは、白土三平の「カムイ伝」連載終了の余韻が残っていた。そこに超個人的で普遍性もなければアート性もないベタベタの現実逃避的な漫画をぶつけたのである。この行為自体、一種の猟奇的行為なのだ。編集長の長井勝一さんは周囲の人の反対を押し切って、僕の漫画を載せてしまった。まさに猟奇に走ったと言うべきだ。 |
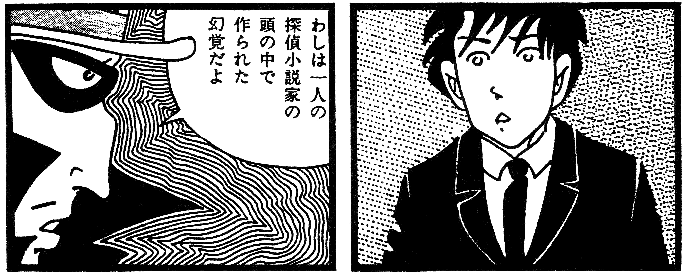
| デビューして二十年以上になるが、一般雑誌からの注文はほとんどない。それほど掲載しにくい漫画なのだ。そしてそれは今でも続いている。漫画界という現実上に、僕の漫画は書き込まれにくかったのである。 さて、デビュー後に猟奇王を作った。怪人二十面相の影響をモロに受けていた。だが、乱歩調のロマンに走れるような時代は遠い昔に終わっているだけに、走るに走れない。語り方も語る内容も両方とも既に終わっていたのである。 それでも漫画の中の猟奇王は、猟奇王と自称してしまったので、二十面相的な大立ち回りを演じなければいけないプレッシャーに苛まれる。そして現実の上では通用しない芸風とは知りつつ、リアルな現実の中に突っ込んで行く。この設定は失敗しか産まない。だからどんなに綿密な計画を立てても、成功しない。それならアドリブで無計画で走り込んでやれということになる。 乱歩の二十面相のような酩酊に近い酔い方が出来ない猟奇王は、怪人を演じきれない。何処か気恥ずかしく感じているのである。猟奇王の仮面の下の素顔は、単に社会人になりたくなかった現実的な僕がいた。 ロマンを追えば追うほどリアルなものが浮かび、現実的なものを追いすぎるとロマンを自然に作ってしまう。 乱歩の登場人物たちは誰もが純粋に役柄を演じている。見事なまでに酔いしれ、恍惚状態だ。そこに純粋なものを感じる。 酔えるものがある作家は純度の高い夢も語れるが、純度の高い現実も見てしまう。 二十面相は古美術品が欲しくて行動した。猟奇王は何も欲しくはなかった。二十面相的な酔い方が欲しかったのだ。 僕が何とか小説を読むことが出来たのは、乱歩の語り口に酔ってしまったからだ。乱歩が語る言葉は、現実の具体的な事柄を差していない。風景や状景さえもが酔っ払っているのだ。そんな現実など何処にもない。だがその言葉は、僕らもはっきりとは把握していないが、何かを差しているのだ。 人生は夢幻のようなものかもしれないが、それは死ぬ寸前に言う台詞だろう。やはり僕らは抜き差しならない現実の上に立っている。それを幻想だと言って宙に浮かせ切れるほど、世間は甘くない。 |

| 同じ事柄でも人によっては現実であり、人によっては夢になる。 乱歩が描いてくれた帝都の風景は、乱歩が書いた時代でもそんな風景ではなかったかもしれない。ともかく語り方が語り方なので、ついついそうあって欲しいと思いながら、乱歩の嘘を受け入れてしまった。あまりにも大げさすぎるので、クスクス笑いながら読んでいたのだが。 乱歩が見ていた帝都の風景から何十年も経過して登場した猟奇王が見る大都会は、乱歩ほどにはロマンチックに語れない風景になっていた。 猟奇王の漫画では明智小五郎はいない。その昔、明智小五郎に文通を希望して断られたことがあるという初老の探偵がいるだけだ。 世の中には探偵と怪人しかいないのだと言いながら、老探偵は頑固なまでに青春時代からの夢に固守する。その夢を捨てた瞬間、彼の人生はいったい何だったのかとなる。 探偵と怪人しかいないという論法は、まるで探偵ごっこをしていた少年の世界だ。確かにそうかもしれない。探偵は現実なのだ。怪人は夢なのだ。そしてそれは稚拙だが分かりやすい理屈なのだ。分かりにくい理屈は理屈ではない。分かりにくいから分かりやすくするために理屈が必要なのだ。分かりにくい理屈はその意味でロマンになってしまう。 猟奇王と老探偵は死闘を演じるが、怪人の存在を支えているのは探偵なのだ。そして探偵を支えているのは怪人なのだ。 理屈は単純であればあるほど理解しやすく迷いがない。それだけに「迷いたい」という気持ちが生じやすくなる。柔軟な構造なら迷いたい気持ちも吸収されてしまう。 |
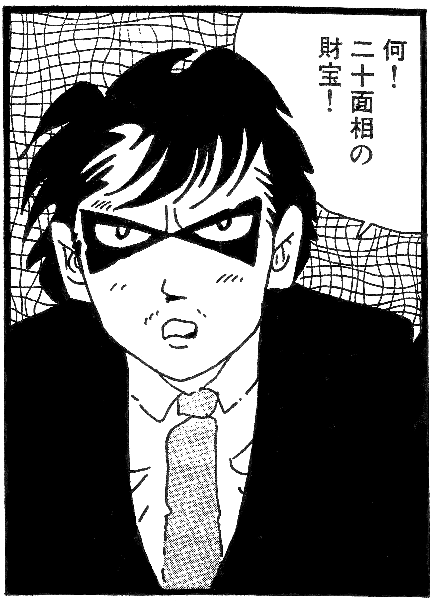
| 乱歩の「屋根裏の散歩者」や「人間椅子」に登場する愛すべき逸脱者達も迷いきっている。方や覗きであり、方や痴漢でしかないのだが、単純さの糸がプツンと切れたとき、とんでもない方向へ振れてしまう。複雑な行為を演じているのだが、やっていることはものすごく単純でダイレクトなのだ。 乱歩にはその背景にロマンがある。そしてそれを演じきってしまえる理性がある。だが僕の猟奇王には、背景に確たるものがない。席が空いているからと言うだけで、行き先に関わりなく列車に乗ってしまったような漫画である。 だから、そこにあるのは雰囲気だけで、手応えのあるものを差していない。僕は乱歩によって探偵(推理)小説の世界を知ったが、トリックよりも、行為にまつわる雰囲気を好んだ。だが雰囲気は、それなりに意味が詰まっていないと味わい深い雰囲気も発酵しない。 そして雰囲気は狙って出せるものではなく、何かの弾みでフッと隙間が空き、そこから漂ってくるものだ。 その意味で僕は乱歩が本当に書こうとしていたこととは違うものを受け取ってしまったのかもしれない。乱歩の雰囲気が好きだった。そして水木しげるの絵の雰囲気が好きだった。そしてその匂いに惑わされて、会社を辞めたのである。二十歳前の僕には小説は書けないが漫画なら書けると思ったからだ。 会社から帰ってきて、乱歩全集を読み耽り、その雰囲気を嗅ぐうちに、この現実とは違うフィクション世界に埋没していった。 乱歩の語るロマンさえも、それ以前の昔を懐かしむような書き方だった。だから猟奇王が二十年前に登場したとき、既に全てが終わってしまったような時代だった。語るべきものが多くなったわりには、充実した語り方が出来るネタが少なくなっていた。 |

| 怪人二十面相的風景は大阪千里の万博の時にほとんど消えたと僕は思った。それでも年代を昭和初期にしたくなかった。やはり現在を舞台にして、終わってしまった怪人の末裔が、どんな夢を見られるのかを語りたかったのだ。夢を語れないと言うことを語ることで、安堵したかったのだろうか。 猟奇王は「語れるような夢などこの現実の何処にもないわ」と嘯きながら、団地の給水塔を眺めている。給水塔の先っちょの膨らみの中に、怪人のアジトがあって、夜中に信号を送っているのではないかとか、地下街の喫茶店の奥で、二十面相の手下だった男の孫が紫禁城の財宝の取引をしているのではないかとか、新興宗教が作ったコンクリート製の大観音像の中に、二十面相の孫娘が監禁されているのではないかとか、フィクション世界をでっち上げていくのである。そして彼は、この現実の何処かにまだロマンが入り込める隙間が空いているのではないか……と、追いかけていくのである。 不思議さや不気味さというロマンの世界も、現実側から見れば不細工であり、不器用なものとして見える。ロマンが現実的なものに、または現実的なものがロマンに切り替わる瞬間に、雰囲気を発散させるようだ。何かのエネルギーが燃焼したときに発する匂いで、そのエネルギーが何を差すのかは分からないが、雰囲気としての匂いだけは感じることが出来るのだ。 言葉でもなく意味でもなく、雰囲気だけが漂っている。 |
話の特集 94年3月号 特集 私的乱歩体験 より