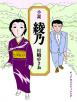画僧
芳念は画僧。絵を描く坊さんだが、出家したわけではない。だから僧侶ではなく、ただの絵師。しかし、僧衣をまとっている。だから私僧。
私立と公立があるようなものだが、見てくれは分からない。それに芳念が立ち寄る界隈では、僧だと思われている。
何処の寺にも所属しておらず、また寺に立ち寄ることもない。
絵師なのにどうして坊主のなりをしているのか。これは僧兵に近いかもしれない。その辺のならず者が僧兵になっていることもあるだろう。
坊主の格好の方が何かと都合がいいらしく、名も芳念と自称。実は僧衣が好きなのだ。
僧衣の絵師なら寺で絵でも描いているのかと思われるが、そういうふすま絵ではなく、簡単な絵。俳画のようなものだ。句に一寸絵を添える程度の。
主な仕事は俳諧。歌の会、連歌など。そのとき、書いた短冊のような紙の隅に、一寸絵を添える。だから書くのは早い。ほとんど一筆書き。文字だけよりも華やか。色がつく感じだ。
歌の会は身分の高い人たちもいるし、そこへ出入りするには坊さんのなりがいいようだ。ただの技術職のようなもので、職人に近い。茶人ではない。絵を描くだけなので。
しかし、その挿絵のような絵、趣があり、下手な歌よりもよかったりする。絵からしたたり落ちる趣。一寸した挿絵に近くなると、そこに独自の世界が生まれたりする。
絵なので読まなくてもいい。見れば一瞬で分かる。その第一印象が全てだ。
添え物の俳画なのだが、絵だけを描いて欲しいと頼む俳人もいる。
また似顔絵も得意で、集まった人たちから頼まれる。
いずれも座興のようなものだが、僧侶姿の絵師というのが洒落っぽく、坊さんが絵を描いている姿と言うのもいいらしい。
道で本物の僧侶とすれ違うこともあるが、軽く会釈する程度。会話が続くと困る。
またお寺近くには寄りつかない。遠回りでも避けて通る。
困ったのはお寺で連歌の会があったときだ。旅の私僧として通すしかない。頭を丸めて勝手に坊さんになっている人もいたので。
芳念は絵は巧みだが、文字は上手くない。そこが不思議。
了
2024年5月23日